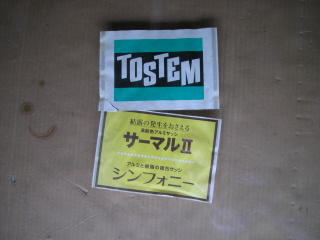テーマ |
写真 |
内容 |
木製框ドア作り |

上下横枠
ガラス受けで角を切除

左右縦枠
芯を外面に配置

欠陥は最小に
小さな死節は妥協の証 |
木枠の材料に選定したのは、赤松のツーバイ材。
赤松としか品名が表示されていなかったのですが、恐らく欧州赤松では?
赤松は、針葉樹でも強靭で最適な樹種。
ただ、杉や桧のように通直で癖の無い材を選べるかどうかがポイント!
ホームセンターの売場では、綺麗なホワイトウッドが山積みされている中で、他の樹種は駆逐されている〜(悲)
サイズは、縦枠が2×4、横枠が2×6のKD材(人工乾燥材)。
これを四角く組んだ枠で、ペアガラス(3−12−3)を抱きかかえる仕組み。
枠へのガラスの組み込み方は、溝掘りではなく角を欠いて正面から押し込むイメージです。
しかし、それでは垂直荷重は支えれても、開閉によって脱落してしまいます。
そこで、木枠と面一になった部分にアルミ板の押さえ材を当てます。
これで、基本構造は出来上がり、吊り込む事が出来る状態となります。
そして、アルミ押さえ材を隠すようにレッドシーダーの外装材を貼って仕上げます。
話が前後しますが、通直な材と言っても、中々、簡単には手に入りません。
全体に捩れている物や木目の通りが悪い物は、使えません。
しかし、無節なんて物は有ろうはずがありませんし、端から端まで一切曲がり無しなんて物もまず有りません。
そこで、必要寸法よりもワンサイズ長い材から使える部分を切り出す事も避けられない方法です。
時には、2サイズって事もあるし、数十本も有るのに使える物が一つも無いって場合も普通にあります。
言葉に矛盾するようですが、売場を掻き回すような事は出来ませんし〜
(言葉を裏返せば、本当に良い商品を取り易く陳列して!)
そこで、こればかりは現物至上なわけで、売場巡りや長期戦を覚悟しなければなりません。
しかし、どうしても避けられないのが、コストと手間とのバランス〜
避けられない小節やヤニ壺等は、配置上で問題なければ妥協も必要です。
(お願い)
もし、売場で材木を吟味する場合には、元通り或いは元以上にきっちりと陳列し直しましょう!
材木は、売場でも生きています。空調された環境で上手く養生された材木はとても優れた素材になります。
|
| 加工後の木枠 |

接合部の様子
縦枠で荷重を受ける

枠全体
ガラスの枠というイメージ |
加工後の枠を仮に配置してみます。
ホゾの兼ね合い、ガラス部の切り欠き、共に問題ありません。
ペアガラスの受け部分の寸法は、掛かり代が25ミリ、厚み分が18ミリ。
ガラス四隅の角は、縦枠の切り込み部分で受ける構造です。
これは、大きさの割りに極小さな寸法ですが、ガラスの荷重が確実に縦枠へ加わります。
次に、その縦枠からは、蝶番でドア枠に力が流れる仕組みですから、上下枠ともう一方の縦枠は、ガラスを蝶番側の縦枠へ引き寄せるのが主な役割となります。
その為、ホゾ接合部への垂直負荷が軽減される事になり、将来的な垂れ下がりに対して有利に働くはずです。
それでは、仮組み。
ホゾがきつくなる位置まで差し込んで見ました。
これも問題なし!後は、叩き込むだけの事です。 |
| ガラス押さえ材 |

ガラス押さえ材
3ミリ厚アルミフラットバーに座掘り

コーキングでコーティング
硬化後に押さえ材として取付け |
アルミ製押さえ材をフラットバーから作ります。
枠組みの中に面一で組み込まれたペアガラスは、木枠へ接着するのではなく、アルミ製のガラス押さえで固定します。
ガラス押さえは、30ミリ幅で3ミリ厚のフラットバー。
ガラス面へは、幅の半分15ミリが被さるようにネジ穴を加工しています。
ネジ穴は、ステンレスの皿ビスが面一に納まるように座掘りを加え、バリなどは綺麗に取除いてあります。
また、ガラスとの接触部には、シリコンシーラントを緩衝材兼、支持材として塗り、コーティングしてあります。 |
| いよいよ組立 |

コーチスクリューで組付け
ホゾを除けて、上下に各2本ずつ

|
仮組みした枠の上に、ペアガラスを静か〜に寝かせて置きます。
ペアガラスは、ユニット化されている為、とても扱いやすいのですが、如何せん重たい〜!
持ち運び時も、垂直に近い間は大した気遣いもいらないのですが、徐々に寝かすに連れ、撓む(たわむ)様子が手元にハッキリ!
最後は、指を挟む〜のではなく、その為に仮組みで寸法に余裕を残していたわけ。
ガラスの落とし込みが無事出来た後は、しっかりと枠を叩き込みます。
これ以後は、道具を落とせばガチャンですから、ベニヤとかダンボールで養生しながらの作業となります。
枠の組付けは、四隅に各2本のステンレスコーチスクリューをねじ込みます。
ネジは、予め用意した丸棒に合わせて開けた穴(座掘り)の底に打ち込みます。 |
| 押さえ材取付 |

隅部の様子
押さえ材で接合部を補助

全体の様子
細かいピッチのステン皿ビス |
組付けた枠、落とし込まれたガラスのいずれも、問題なく組み上がり、次に、ガラス押さえを取付けます。
押さえ材の取付けは、ドライバーのビットでガラスを割らないように慎重に。
これで、木枠とペアガラスが一体化しました。
試しに、全体を持ち上げてみると、捩れたり撓む感じは無くて、ガッチリとした手応えが伝わってきます。 |
| 外装材の取付 |

外装材は接着
全体ではなく外周面のみ

下枠には水抜き穴
穴とは言え、実は塗り残し |
構造的には、出来上がったとは言え、アルミ押さえ材剥き出しでは、デザインが成り立ちません。
そこで、仕上げ材としてワンバイサイズのレッドシーダー材を貼ります。
レッドシーダー材は、腐朽に強く外装材に打って付け!
しかし、木製ドアの外装と言えば、確実に傷みますので、将来の取替えも簡単に出来るようにします。
また、薄くて柔らかい材ながらも、構造的には余力を期待したいところです。
そこで、選んだ方法は、シリコンシーラントによる接着。
ビス等は、1本も使いません!
カートリッジガンで搾り出して、そこに材を押付けるだけ〜
要するに、作業も簡単でした〜!
強いて言えば、コーキングが沢山必要な事ぐらい?
と言うのも、この面は、アルミの押さえ材が有るので、3ミリ以上の高さで塗らないと圧着させれない理屈です。
接着する部分は、枠の外周際の一筋。
これで、アルミ押さえ材と同じ高さに揃えて圧着すれば、綺麗な外装面が出来上がります。
下枠には、万一、どこかから水が回った時の為に、水抜きを3ヶ所設けています。
|
| 接着部を仕上げる |

内外でコンビデザイン |
まるでホゾ組みのように綺麗に貼れました。
シリコンシーラントの仕上げは、合わせ部のはみ出した部分や足らない部分をヘラで均し、面一か少し控えた状態で目立たぬようにしておきます。
この後、完全硬化まで、触らずに養生させます。 |
| 防腐塗装 |

外装はキシラデコール塗布 |
養生が済めば、防虫防腐塗装で最後の仕上げ。
ガラス面は、ダンボール等を枠に差し込みながら、簡単にマスキングが出来、反対側は、合わせ目で見切れるので作業が捗ります。 |
| ガラス周りコーキング |


|
合わさった部分をガラス側から見ると、僅かにガラス押さえの端部とペアガラスのユニット接合部が見えます。
中々、クリーンで良い雰囲気なのですが、このままでは雨水が内部に浸入してしまいます。
そこで、この部分は、シリコンシーラントでコーキングするわけですが、少し気をつける点が‥‥‥
それは、この部分の外装材とガラス面には、押さえ材の厚み分(3ミリ)の隙間が有ります。
その為、このままの状態で普通に充填すれば、奥の奥までしっかりと入ってしまいます。
それでは、簡単に外装材を取替え出来なくなります。
そこで、ガラス面にマスキングテープを貼った上で、出来るだけコーキングガンを立てて、奥に入り過ぎないように塗り付けます。
もちろん、バックアップ材を入れても良いのですが‥‥‥
これで、外装材は、内外二重のシール材で接着された事になり、ガッチリ一体化しています。
しかし、将来の取替え時には、シールの端までカッターナイフの刃が届くので、切取る事が可能です。
|
| 特殊なドアキー |

ドアキーの構成部品
ホームセンター店頭では、見かけません

試し掘り
実際の穴径で先端寸法を修正 |
このドアは、建物のエントランスドアとなる条件です。
その為、室外から操作出来るロックが必要なわけです。
ところが、ドアロックは、一般的なシリンダー錠が使えません。
これは、当初に構造を決めた時からわかっている事。
縦枠が2×4材で89ミリ幅の中に、25ミリ分ガラスが入り込む構造。
しかも、ドアの厚みは50ミリ以上で、断面部分には、合わせ目まで有る。
そこで、登場するのが、小さいセットバック、大きなドア厚という二重苦に対応した特殊な錠。
インターネットで調べました。(本当に便利です〜)
名前は、面付け本締錠の中の1種類でミワロック製。
対応ドア厚は、42〜66ミリまで数種類有ります。
以上をネットで調べた上で、ホームセンター オージョイフルで取寄せてもらいました。
写真右端がベースプレートで、木製、金属製、いずれのドアにも対応可能。
その隣の錠本体は、ドアの室内側表面にベースプレートを介して取付けられます。
さらに、その隣の筒状の物が、シリンダー部。
ドアの厚み分の長さが有り、室内面の本体と組合わさって機能します。
取付けに際しては、本体と差込部のオフセットが大きいだけに、精度が悪いとシリンダー部が、グラグラしてしまいます。
そこで、しっかりとサポートさせる為に、ドリルの振れの誤差分も加味して、きっちりと穴を開けます。 |
| ドアキー取付 |

貫通したシリンダー取付穴
アルミ押さえ材の際をギリギリセーフ

ガードプレート
シリンダーの打ち抜かれ防止

回り止め
シリンダー際に面一の金属ピン

本体側
この状態が開錠状態 |
ドアキー本体の取付けは、内側の赤松材となる為、しっかりとネジ止め出来ます。
しかし、面付け錠は、本体がドア内面に露出している為、正面から打ち抜かれる危険性が有ります。
そこで、シリンダー部のリングがすり抜けないピッタリのサイズで、ガードプレートを作製し取付け。
ガードプレートは、2ミリ厚のステンレス板で超頑丈!
プレートは、正面から皿ビスを座掘りで固定しています。
しかし、それでは、ネジを外して回転させればテコとしてプレートを利用出来ます。
シリンダー部は、本体側からビス止めされているので簡単には抜けませんが、念のために〜
シリンダーが被さる位置で、ピンが打ち込まれています。
その為、簡単には回転しません。
と言うような事をこだわっていますが、ガラスを割ればイチコロ〜!
まあ、普段使用時のキズ予防って事ですね〜♪
*当初からドアロックの取付けが決まっている場合は、縦枠単品状態で作業すると簡単です。 |
蝶番取付
(別のドア写真を引用) |

丁番
強度優先の機能的な大型丁番

丁番の配置
4枚吊りで均等配置 |
ドア側への取付けは、構造材である赤松材のみにネジ止めし、ドア吊り込み状態でも外装材の交換が可能です。
取付部は、当然、丁番の厚み分を欠き込んでいますが、その事に頼るようでは、とても耐えれるものではありません。
では?
大型のカラーステンレス丁番による4枚吊りで万全! |
完成! |

取っ手材料
その辺に有りそうな曲がり木

取っ手とドアロック
市販品では出来ない配置 |
最後のおまけが、ドアハンドルの取付け。
ドアロックが、普通のインテグラル錠と異なる独立タイプとなる為、別途に取っ手が必要です。
そこで、問題となるのが、そのデザイン!
デザイン要素の強いドアにあって、さらにデザインを決定的に左右する〜
取っ手一つで、アーバンにもワイルドにもクールにもアンティークにも‥‥‥なってしまうから。
簡単なのは、店頭の市販品から選ぶ方法ですが‥‥‥
空の握りやレバー錠を付けても、ドアサイズや雰囲気に馴染みません。
大体、こういったサイズは、店舗出入口やテラス戸といったスペシャルな場所で見かける様な物です。
そのようなケースでは、金属や木製の大きなバーやプレートのハンドルが付いている場合が多い。
そこで、身近なデザインではなく、ガッチリと使いやすくて存在感の有るデザインがやはりベスト!
しっかりとしたブラケットと大きな持ち手〜
丸棒では簡単ですが、平均点って感じですので‥‥‥
でも、丸棒の途中に適度な間隔でブラケットが取付けられたデザインは、端にペットのリードや帽子、買い物袋を掛けたりと楽しそう。
もしかすると回覧やプレートを下げたりとコミュニケーションにも‥‥‥
そこで、取り置きしていたサルスベリの枝を利用して、しっかりとしながらも手に優しい触感の仕上りに。
表面を磨いた上で、ワトコオイルで塗装しています。
取付けは、市販の手摺用ブラケットを使用。
材を3次元的に座掘りし、取付部の平面を出しています。
また、上手く曲がりを利用することで、シリンダー正面を避けつつ、付近のガラス面を手荷物等からガードする役目も持たせています。
もちろん、機能的なドアが、ワイルドなイメージに変身しているのは、御覧の通りってわけ!
|