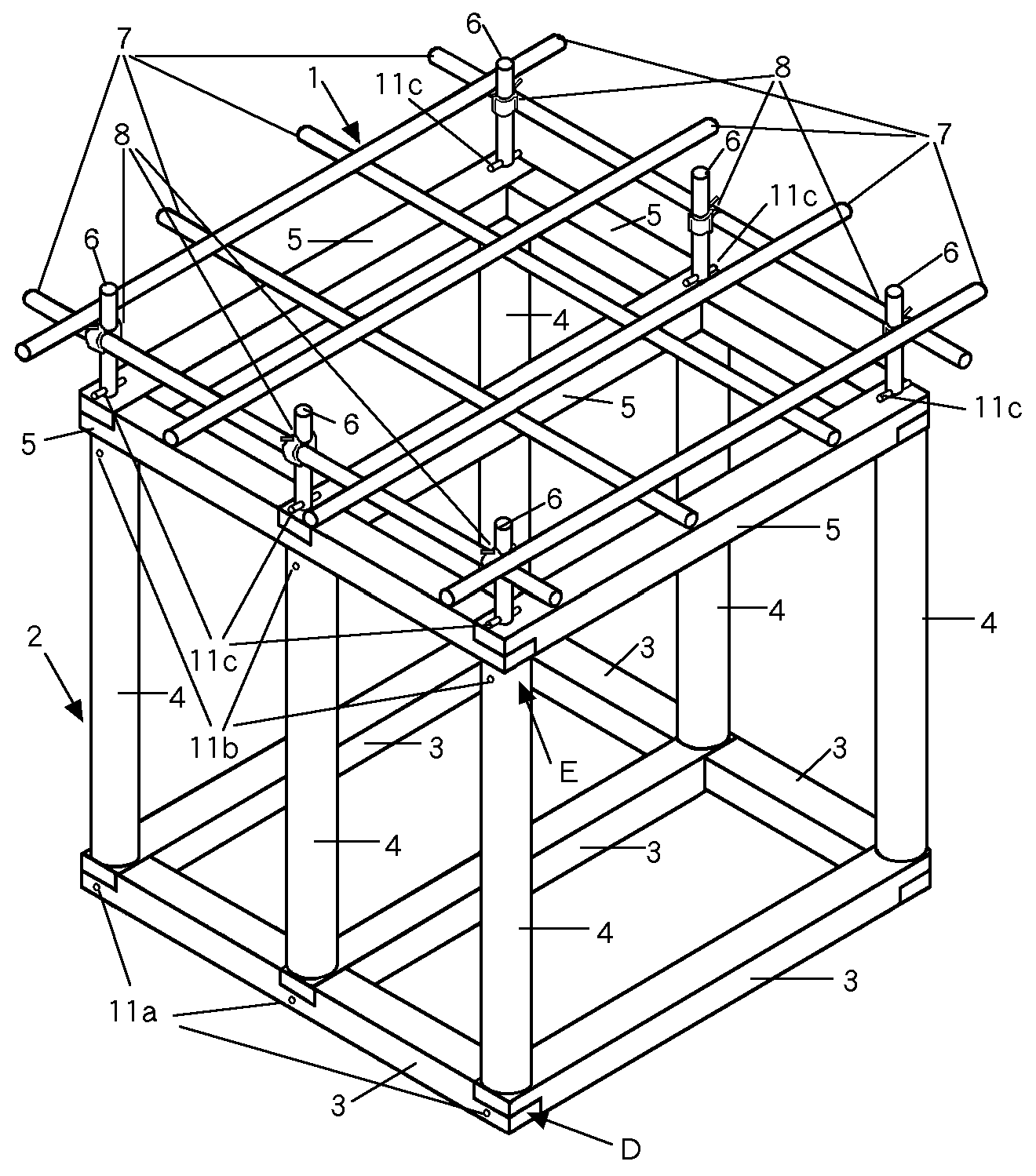 |
基本的な構造例
|
| 技術要件 |
まず初めに、本装置における下枠(3)、柱(4)、上枠(5)から成る木造部分を木造軸組構造体(2)、鋼管(7)により網状を成す部分を衝撃吸収網(1)、衝撃吸収網(1)と木造軸組構造体(2)を接続する鋼管を特に鋼管柱(6)と定義し、以後の説明において使用する。
この室内軸組構造体は、大きくは、木造軸組構造体(2)と衝撃吸収網(1)の二つの部分からなる事を特徴とする。
まず、充分な強度を有する材木からなる下枠(3)、柱(4)、上枠(5)の構造材により充分な強度の木造軸組構造体(2)を作る。
さらに、木造軸組構造体(2)上部に鋼管柱(6)を設け、既存天井面(C)の直下に普通品の足場鋼管等の鋼管(7)を網状に接合した衝撃吸収網(1)を取付ける。
この際に木造軸組構造体(2)と衝撃吸収網(1)の間には、緩衝距離(A)を適当に確保するようにする。
以上を既存建物の既存室内床面(B)上に、建物から独立した状態で設置する事により生存空間の確保を図る。
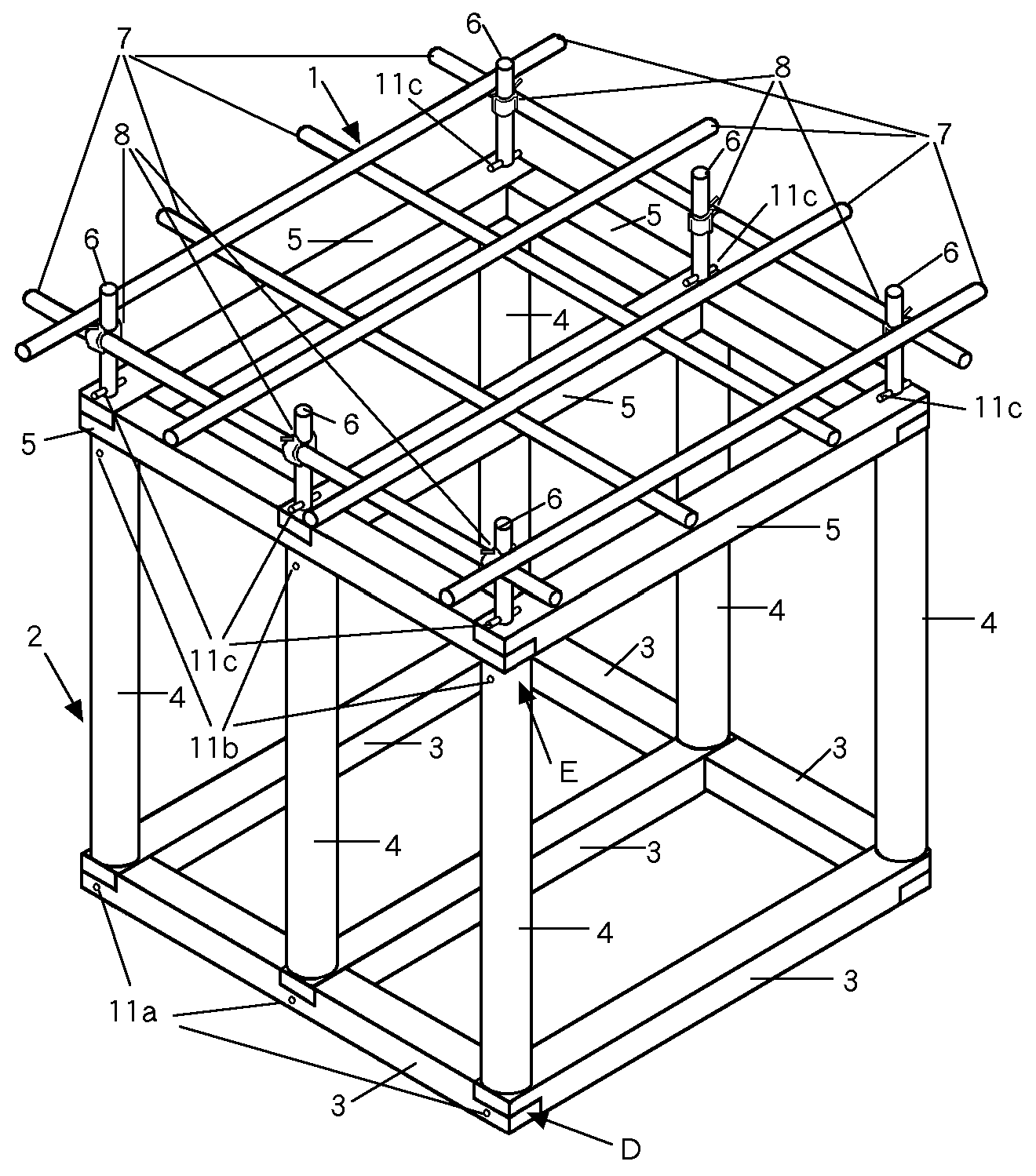 |
基本的な構造例
|
<補足>
以下、本装置の建物崩落時の生存空間となる室内軸組構造体について、上図に基づいて補足説明する。
既存室内床面(B)上に下枠(3)を据え置き、その下枠(3)に柱(4)を立てる。
下枠(3)が、床面と接触する部分には、フェルト様の保護材を必要に応じて取付ける。
柱(4)の頂部には上枠(5)を梁勝ちで取付け、木造軸組構造体(2)が出来る。
次に、衝撃吸収網(1)は木造軸組構造体(2)の上部で、鋼管柱(6)により緩衝距離(A)を適当に設けて、既存天井面(C)直下に取付けられる。
鋼管柱(6)は、穿孔、又は、取付座によって上枠(5)に取付けられる。
衝撃吸収網(1)は鋼管(7)を溶接、金具のいづれで接合しても良いが、衝撃吸収網(1)と鋼管柱(6)との取付けについては、普通品の締付け金具(8)を使用する。
木造軸組構造体(2)に使用する材木は、一般の建築用材で良いが、既存室内床面(B)と接する下枠(3)の一面を除いては、平面でなくとも良い。
又、材木の太さについても、間伐材等の小径木を用いる場合は、柱(4)本数を増やす等の強度に対する整合性を取れば良い。
材木の接合方法については、仕口加工、金具使用、両者併用のいづれであっても、充分な強度が有れば良しとする。
さらに、構造は複雑になるが、木造軸組構造体(2)は、方杖、筋交い、火打ち等の補強材を入れる事でより強固になる。
又、鋼管(7)は、足場鋼管等の充分な強度のある市販品使用し、インテリア性を高める為には、塗装して使用する。
以上は、使用者の意思によって選択出来る部分であり、住宅に種々の工法が存在する事と変わり無く、求める安全性と掛かる費用や日常使用への支障、そして建物への負荷についてのバランスを考慮して自由に選択すれば良い。
| プロトタイプの紹介 | ||
 |
 |
 |
この事例は、基本的特長を有する事例である。 |
||
この基本構造を有するプロトタイプにおける設計数値は、木造部分が縦横高さ共に一辺が2メートルの立方体である。 鋼管部分を含めた最大寸法は、縦横220センチ、高さ240センチ、目標重量は、約260キログラムである。 設置面積は、一辺を2メートルの4平方メートルであるから約65キログラム/平方メートルとなる。 これは、テーブルに平均的な大人4人が着席した場合と同程度の軽重な負荷である。 そこに、若干の居住者並びに負荷物を加味した場合にあっても、建物に対して顕著な負荷を与える物では無い。 しかしながら、当該装置を設置する居室においては、その他の家財を整理する事を推奨する。 本プロトタイプにおいては、105正角桧乾燥材を使用し実測@11.5kg×16本で184kgである。 鋼管は、単管足場材(φ48.6ミリ2.3ミリ厚)計24メートルを使用し2.63kg/mより63.12kgである。 以上により、クランプを用いる鋼管接合においても、全体としての設計荷重はほぼ達成している。 |
||
Copyright 2004 Makoto Nagai. All rights reserved